医学を勉強するうえで、糖や脂質やタンパク質などの栄養分がそもそも何なのかを把握しておくことはとても大事です。
これが頭に入ってないと、糖などを合成する器官を学んだり、輸送する器官を覚えたりしてもイマイチイメージができず、定着しません。
糖とは?

糖は炭水化物のもとであり、動物が活動するためのエネルギーになります。
糖にはグルコース、フルクトースなどのように-ose(-オース)の発音が語尾につきます。
糖は、リボースやグルコースなどの単糖と、
2個の単糖がくっついた形のスクロースやガラクトースなどの二糖と、
数百個の単糖がくっついた形のデンプンやセルロースなどの多糖があります。
では、糖はどのような形で生体内に存在しているのか?植物と動物に分けてみていきます。
植物の貯蔵多糖
植物にはグルコースという単糖がくっついて形で存在しています。
グルコースは2通りのくっつき方をします。
枝分かれをしないで直線的にくっつくとアミロースと呼ばれます。
枝分かれをするとアミロペクチンと呼ばれます。
そしてアミロースとアミロペクチンはまとめてデンプンと呼ばれます。
つまり、植物はデンプンの形で糖が貯蔵されていますが、その正体はグルコースがくっついたアミロースやアミロペクチンであるということです。
動物の貯蔵多糖
動物もグルコースという単糖がくっついて存在しています。
動物の場合は、グルコースは著しく枝分かれしながらくっついてグリコーゲンになり、これが様々な組織に蓄えられます。
植物に比べるとシンプルですね。
脂質とは?
脂質は脂肪・リン脂質・ステロイドなどの種類があります。
この種類によって働きが異なります。
脂肪とは
脂肪は主にエネルギーを貯蔵する働きをもちます。先ほど記述した同質量のデンプンに比べて、2倍以上のエネルギーを貯蔵することができます。
また脂肪組織は物理的な衝撃や温度変化から内臓を守る役割も果たします。
脂肪は脂肪酸とグリセロールがくっついてできています。
リン脂質とは

リン脂質は細胞膜の材料になります。
リン脂質は親水性である頭部(画像の円部分)と、疎水性である尾部(画像の長方形部分)からなります。(画像のリン脂質は一対が向かい合っている状況です。)
細胞膜の構造について詳しくはこちら
ステロイドとは?
ステロイドは多様な機能を持ち、生物学的なプロセスにおいて重要な役割を果たしています。
以下にいくつかのステロイドの例を挙げます。
- ステロイドホルモン
ステロイドホルモンは、生物の体内で生成される化学物質で、重要な生理的機能を制御します。
例)コルチゾールやアルドステロンなどの副腎皮質ホルモン、エストロゲンやテストステロンなどの性ホルモン
これらのホルモンは、代謝調節、生殖機能、ストレス応答などに関与しています。 - コレステロール
コレステロールは、細胞膜の構成成分として重要なステロイドです。また、ビタミンD、胆汁酸、性ホルモンなどの生合成にも関与しています。しかし血液中にコレステロールが過剰に存在すると、動脈硬化の原因になると言われています。
タンパク質とは?

タンパク質の構造
タンパク質は、アミノ酸がたくさんくっついてできています。
タンパク質は、階層的なレベルで複数の構造を持っています。
- 一次構造
一次構造はタンパク質のアミノ酸配列の順序を示します。
アミノ酸はペプチド結合によってつながり、直線状のポリペプチド鎖を形成します。 - 二次構造
二次構造はポリペプチド鎖内のアミノ酸の局所的な配列パターンです。代表的な二次構造にはαヘリックスとβシートがあります。これらは水素結合によって安定化されます。 - 三次構造
三次構造はポリペプチド鎖全体の立体的な形状を表します。タンパク質は特定の折りたたみパターンを取ることで形成されます。水素結合、塩橋、水酸基間の相互作用、疎水性相互作用などが関与します。 - 四次構造
四次構造は、タンパク質が複数のポリペプチド鎖からなる場合に現れます。これらの鎖は相互作用して、多量体を形成します。
例)ヘモグロビンは二つのアルファ鎖と二つのベータ鎖からなる四量体です。
このような階層的な構造は、タンパク質の機能に重要な役割を果たしています。構造の変化や異常な構造は、タンパク質の機能の喪失や病気の原因となることがあります。
例えば目玉焼きをつくるときに、生卵が加熱されることで卵黄や卵白は変性して性質が変わります。
このように温度やpHの変化などで立体構造が変わることを変性といい、本来の働きが失われることがあります。
タンパク質の働き
その働きは様々で、どれも生体にとって必要なものです。
- 構造タンパク質
細胞骨格のもととなり、強度を維持する役割を果たします。
例)コラーゲン、エラスチン - 酵素
化学反応を触媒することで、反応速度を高めます。
例)ヒトが植物から糖を摂取できるのは、デンプンを分解する酵素を持っているからです。 - 輸送タンパク質
細胞膜を通じて物質を輸送させるためのチャネルやポンプがあります。
他にも、血液中で酸素を輸送するヘモグロビンのように、体内で物質を輸送するタンパク質もあります。
例)イオンチャネル、プロトンポンプ、ヘモグロビン
チャネルやポンプについて詳しくはこちら - ホルモン
体内の様々な動作を制御します。
例)インスリンは他の組織に働きかけて、グルコースを取り込ませることで血糖値を下げます。 - モータータンパク質
絨毛などの様々な器官の運動を引き起こします。
例)アクチンとミオシンは連動して筋肉の収縮を引き起こします。 - 免疫グロブリン
体内で抗体として働き、ウイルスや遺物に対して免疫応答を引き起こします。
例)IgA、IgD、IgE、IgG、IgM - 受容体タンパク質
細胞の信号や化学的な刺激を受容します。
例)神経細胞の受容体は、別の神経細胞からのシグナル分子を受け取ります。 - 貯蔵タンパク質
アミノ酸を貯蔵する働きをします。必要な時に分解されて、アミノ酸として利用されます。
例)乳液中に含まれるタンパク質は、哺乳類の乳汁中で貯蔵される貯蔵タンパク質です。これらのタンパク質は乳幼児の栄養源となり、成長と発達に必要なアミノ酸や免疫因子を提供します。
まとめ
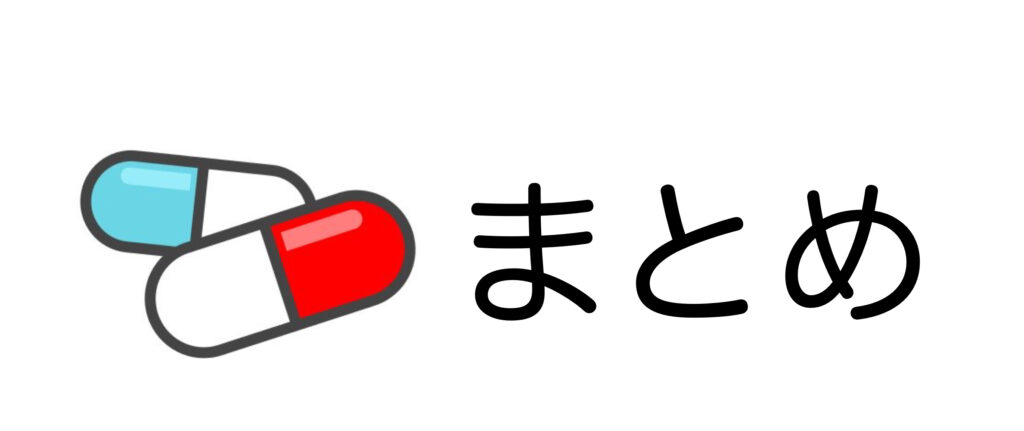
- 糖は様々な活動をするためのエネルギーになる
- 脂質はエネルギーを貯蔵する役割をもち、脂肪やリン脂質やコレステロールなどがある
- タンパク質は立体的な構造をとり、様々な種類があり、それぞれ機能をもつ
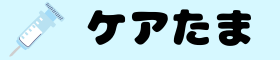



コメント